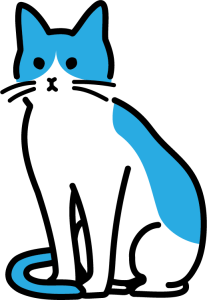会員病院向け情報
- トップ
- 会員病院向け情報
猫の認知症と栄養
2025年5月25日
2025年5月20日配信
《本研究の主題・目的》
本レビューは、猫の認知機能と栄養の関係について、進化的視点と歴史的背景を踏まえながら論じたものである。猫の認知に関する研究は犬よりも遅れているが、近年注目が集まり、加齢性認知機能低下(CDS)とその予防・管理における栄養の役割に関する議論が進められている。
《猫の進化と社会性の特徴》
○猫(Felis catus)は、約1万年前に中東のリビアヤマネコ(Felis silvestris lybica)から家畜化されたと考えられている。
○家畜化の初期段階では「自己家畜化」が進み、より人に寛容な個体が定住するようになった。
○通常の野生ネコ科動物は単独生活を好むが、イエネコは条件に応じて群れを形成することが可能で、柔軟な社会性(facultative sociality)を示す。
《猫の栄養的特性と進化》
○猫は**完全な肉食動物(obligate carnivores)**であり、タンパク質の要求量が非常に高い。
○タウリン、アルギニン、ビタミンA・D、ナイアシン等を合成できず食餌から摂取が必要。
○糖質代謝能力は限定的であり、主にタンパク質と脂肪からエネルギーを得る。
○魚油(DHA・EPA)や抗酸化物質(ビタミンE、Cなど)は加齢に伴う脳機能の低下予防に重要とされている。
《猫の認知機能の現状》
○猫の認知は感覚認知・記憶・問題解決能力・社会的認知・感情理解・学習能力など多岐にわたる。
○人間の視線や指差しに反応する能力があり、**飼い主との絆や愛着行動(secure/insecure attachment)**も確認されている。
○ただし犬に比べると人間の感情に対する反応は控えめであり、社会的参照や課題解決での人依存行動は少ない傾向。
○音声・フェロモン・視線などを用いて人と双方向のコミュニケーションが可能である。
《加齢と認知機能低下(CDS)》
○**11歳以上の猫の28%、15歳以上の50%**にCDSに該当する兆候がみられる。
○行動変化はVISHDAAL(徘徊、社会的変化、睡眠リズム変化、排泄異常、見当識障害、活動レベル低下、不安、学習記憶障害)で記述される。
○CDSは老齢性脳萎縮、酸化ストレス、βアミロイド蓄積、コリン作動性機能低下と関係。
《栄養と認知機能の関連》
● 栄養素と行動
○トリプトファンやチロシン:セロトニンやドパミンの前駆体。ストレス耐性や攻撃性の低減に寄与。
○**α-カソゼピン、L-テアニン、MCTs(中鎖脂肪酸)**などのサプリメント:不安・ストレス軽減に一定の効果。
○**腸内細菌叢と脳の相互作用(脳-腸-マイクロバイオーム軸)**の重要性が指摘されている。
● CDS対策としての食事療法
○ビタミンE、C、B群、タウリン、アルギニン、L-カルニチン、抗酸化物質、ω-3脂肪酸(DHA・EPA)を含む食事は行動改善や寿命延長と関連。
○抗酸化栄養素は酸化ストレスを軽減し、神経保護作用を持つ可能性。
○CDSの進行後は、環境や食餌の変更に対する耐性が低下するため、早期介入が望ましい。
《薬物療法》
○現在、CDSに対して猫専用の承認薬は存在しない。
○犬用薬(セレギリンなど)のオフラベル使用や**SAMe、メラトニン、降圧剤(テルミサルタン)**等が提案されているが、慎重な投与管理が必要。
《今後の展望》
○猫の認知と栄養に関する研究はまだ初期段階。
○CDS予防に向けた栄養介入やサプリメントの組み合わせ効果の研究が今後の課題。
○飼い猫、外飼い猫、野良猫間の社会性・認知能力の比較研究も今後の注目分野である。
《結論》
猫の健康と福祉を考える上で、身体的健康だけでなく、認知的・情緒的健康の評価とケアが不可欠である。加齢による認知機能の低下(CDS)に対しては、早期の認識と、栄養・環境・薬物を組み合わせた包括的アプローチが求められる。
※『Feline Cognition and the Role of Nutrition: An Evolutionary Perspective and Historical Review』
著者: Allison P. McGrath, Daniel J. Horschler, Leslie Hancock